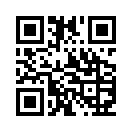2008年03月02日
全国ボランティアコーディネーター研究集会に参加
北は北海道から南は沖縄まで、日本全国から研修に参加されており、クロージングの全体会には400人ぐらいが一同に会しました。
そもそも「ボランティアコーディネーター」ってなんやねん!?って感じですが、普段の業務の中で、コーディネーションは自然と行われていることで、例えば、「この文書を翻訳してほしいんだけど、してもらえる方はいますか?」と問い合わせなり、依頼なりが来る。そして、ボランティア登録をしてくださっている人や思いつく方に連絡をとり、質問・依頼内容をお話する。そして、お願いできるか聞いて、OKだったら、問合せしてくださった方に連絡する。
よくあることですが、これも十分ボランティアコーディネートしているのです。
ただ、そのコーディネーション力や専門知識があるのとないのでは、どれだけボランティアさんの力を生かし、地域社会に貢献できるかどうか?が違ってくるのです。
JVCAさんの定義もあるので、また詳しくはJVCAさんのHPをご覧いただければと思いますが、ホントにいい「学び」になりました。
1日目は「グループをチームに変えるファシリテーターをめざせ」の分科会に参加。
「貿易ゲーム」と「ワールドカフェ」のワークショップでは、分かれたグループでテーマを共有し、そのことにより「グループ」が「チーム」になることを体感しました。
2日目の今日は、「本気の多文化共生」をテーマに、和歌山県国際交流協会の事例を聴き、それぞれの団体や組織でのボランティアコーディネーションについて話をしました。
どの分野のどんな団体でも、ボランティアの存在は社会を変える大きな存在であること。そして、人を元気にし、社会を元気にする力があることを再認識しました。
また、ここ最近よく言われる「協働」についても厳しい言葉がでました。でも、すごく納得。
「学びあう姿勢のない人とは協働できない」
ほんと、そうですよね。一人歩きしている「協働」って言葉ですが、お互いに学ぼう、ともに創ろうという気持ちがないとできませんよね。
ということで、このボランティアコーディネーターという立場を社会で認知してもらうため、検定ブームに乗ってではないけど、今年の8月には「ボランティアコーディネーター認定試験」も行われるそう。
このブログの活動紹介のところにも書いているように、やはり「人が元気なまちは、まちも元気」なんです。
私たちのような民間の国際交流団体ができることって、無限大∞ですね!
国際交流に関する、いろいろな経験やノウハウをお持ちの方、出番ですよ!
Posted by kis at 21:13│Comments(0)